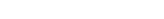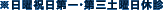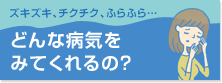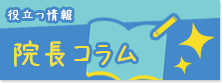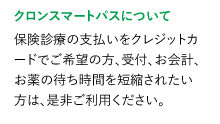半世紀近く前、私が脳神経外科医になったころは脳卒中と言えば脳出血が多かった時代でした。その後、脳梗塞が増え、現在は脳出血の頻度は減少しています。日本脳卒中データバンク報告書2021年によりますと病型分類で脳梗塞は全体の72%、脳出血は20%と脳梗塞が圧倒的に多くなっています。脳出血が少なくなった要因としては、血圧の低下と総コレステロールの上昇があると考えられております。
現在、脳梗塞の発症の原因となる四つの危険因子として、1.高血圧症2.高コレステロール血症(脂質異常症)3.糖尿病と4.喫煙があげられています。最大の因子である高血圧症に関しては、久山町研究で、血圧が140以上の方が130台の方に比べ、脳梗塞の発症率が約2倍になることが示されております。血圧を制することが脳卒中の予防の大きなカギとなります。MRIで未治療の高血圧症やその他の危険因子をお持ちの方は隠れ脳梗塞、虚血性病変である白質病変が多くみられます。さらに、びまん性の広範囲な白質病変になると、認知障害、歩行障害をきたします。元気な日常生活を少しでも長く続けるためにはこれらに危険因子(とくに高血圧症)をコントロールすることが大切です。MRIで隠れ脳梗塞、白質病変がみられた方は、進行してないかどうかを見る意味でも定期的な脳のチェックをお薦めします。